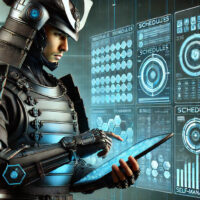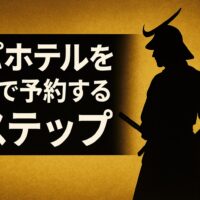企業における社内報の役割は、情報共有やコミュニケーション促進だけでなく、組織の活性化にもつながる重要なツールじゃ。
しかし、せっかく作成しても「社員に読まれない…」という課題に直面することも多い。
本記事では、読まれる社内報を作るための面白い企画を目的やテーマ別に紹介する。
また、ネタ切れを防ぐアイデアの探し方や、発行のコツについても解説するゆえ、社内報担当者はぜひ参考にされよ。
目次でござる
社員に読まれる社内報のポイントとは?
社内報を発行しても、「社員が読んでくれない」「情報が一方通行になっている」と感じることはないか?
読まれる社内報を作るためには、内容の工夫や発信の仕方にポイントがあるのじゃ。
社内報の役割と目的を再確認
社内報には、以下のような役割と目的がある。
✅ 企業理念やビジョンの共有
→ 経営層の考えを伝え、組織の方向性を統一する
✅ 部署間のコミュニケーション促進
→ 他部署の活動を紹介し、社内の理解を深める
✅ 社員のモチベーション向上
→ 成果を認め、表彰することで、社員のやる気を引き出す
✅ 業務に役立つ情報の共有
→ 新しい制度やツールの導入情報を知らせる
読まれる社内報にするための工夫
1. 視覚的にわかりやすいデザインにする
写真やイラストを活用し、直感的に理解しやすくする
見出しや色分けを工夫し、読みやすさを向上させる
2. 社員が関わるコンテンツを増やす
社員インタビューや座談会形式の記事を取り入れる
コメントや意見を募集し、参加型の社内報にする
3. スマホやWebで読めるようにする
紙媒体だけでなく、社内ポータルサイトやメール配信を活用する
短い動画コンテンツを組み合わせるのも効果的
4. 企業の文化や価値観を反映する
会社独自の文化を取り入れ、社員が共感しやすい内容にする
社内イベントや成功事例を積極的に紹介する
社員に読まれる社内報を作るために
✅ 目的を明確にし、伝えたい情報を整理する
✅ 社員が参加できる仕組みを作り、双方向のコミュニケーションを意識する
✅ 読みやすいデザインやフォーマットを工夫する
面白い社内報企画の選び方とポイント
社員が思わず読みたくなる社内報を作るには、企画の選び方が重要じゃ。
面白い企画を取り入れ、読みやすさや参加しやすさを意識すれば、自然と関心を集める社内報が作れる。
読まれる記事にするための工夫
1. 目的に合った企画を選ぶ
社内報の目的によって、適した企画は異なる。
例えば、以下のように目的別に企画を選ぶのがよい。
✅ 社内コミュニケーションの活性化
社員インタビュー企画(新人・ベテラン・経営層)
他部署紹介・仕事の裏側レポート
✅ 企業理念の浸透・文化の共有
創業エピソードや経営理念のストーリー化
会社の歴史を振り返る「○○年前の今日」企画
✅ モチベーション向上・働きがいの創出
社内表彰・成功事例の紹介
「この人に聞きたい!」社内のスペシャリスト紹介
2. 参加型の企画を増やす
社員が関わる企画を取り入れると、読者の関心が高まる。
✅ アンケートを活用する
「今、気になっていること」調査
「社内で改善したいこと」匿名投票
✅ 社員同士の交流を促す企画
社内の「推しメン」紹介(尊敬する上司や同僚を推薦)
おすすめのランチスポット紹介(写真投稿付き)
3. 季節ごとのイベントを企画に盛り込む
社内報には、季節感を取り入れると親しみやすくなる。
✅ 春:新入社員歓迎特集、社内お花見レポート
✅ 夏:社員の旅行記、夏季休暇の過ごし方
✅ 秋:社内運動会・レクリエーションの紹介
✅ 冬:クリスマスパーティー、忘年会の振り返り
面白い社内報を作るために意識すべきポイント
✅ 目的に応じた企画を選び、方向性を明確にする
✅ 社員が参加しやすい企画を増やし、関心を引きつける
✅ 季節ごとのイベントを活用し、読みやすさを高める
テーマ別!社内報に使えるアイデアと企画集
社内報を充実させるためには、テーマに沿った多彩な企画を取り入れることが重要じゃ。
ここでは、「定番」「社員参加型」「ビジネス系」「季節・イベント系」の4つのテーマに分け、具体的な企画を紹介する。
① 定番の社内報企画(毎号掲載しやすい鉄板ネタ)
✅ 社長メッセージ/経営陣インタビュー
→ 経営方針や企業のビジョンを伝え、社員のモチベーション向上に役立つ
✅ 社員紹介(新入社員・ベテラン社員・他部署のメンバー)
→ どんなメンバーが働いているのかを紹介し、コミュニケーション促進につなげる
✅ 社内ランキング
→ 「人気の福利厚生ランキング」「みんなが使っている便利なツール」などを紹介
✅ 社内掲示板コーナー
→ ちょっとした社内ニュースやお知らせを掲載
② 社員参加型企画(読者の関心を引きつけるコンテンツ)
✅ 「私の1日」リレー企画
→ 社員が交代で1日のスケジュールを紹介することで、仕事内容への理解を深める
✅ 「この人に聞きたい!」社内のスペシャリスト特集
→ 業務に役立つ知識を持つ社員にインタビューし、ノウハウを共有
✅ 「社内の推しメン」推薦企画
→ 「この人がいると助かる!」という社員を匿名で推薦し、感謝の気持ちを伝える
✅ 社員の趣味・特技紹介
→ 「休日の過ごし方」「特技・資格自慢」などを紹介し、交流を深める
③ ビジネス・業務系の企画(仕事に役立つ情報発信)
✅ 成功事例&業務改善アイデアの共有
→ 各部署の成功事例や業務効率化のコツを紹介
✅ 「知っておきたい業界トレンド」特集
→ 業界の最新ニュースや今後の動向をまとめる
✅ 新制度・ルールの解説コーナー
→ 社内の新制度や変更点をわかりやすく説明し、周知徹底する
✅ 「このツールが便利!」業務効率化アプリ紹介
→ 仕事がはかどる便利なツールやアプリを紹介
④ 季節・イベント企画(社内の雰囲気を盛り上げる)
✅ 新年度特集(4月)
→ 新入社員歓迎インタビュー&入社式レポート
✅ 夏の特集(7月~8月)
→ 社員のおすすめ旅行スポット紹介、夏季休暇の過ごし方
✅ 秋のイベント(10月~11月)
→ 社内運動会・ハロウィンイベントの写真レポート
✅ 年末年始特集(12月~1月)
→ 忘年会&新年の抱負、社員アンケート「2025年の目標」
使えるアイデアを取り入れ、読まれる社内報に
✅ 定番企画で安定した情報発信を行う
✅ 社員参加型のコンテンツを増やし、関心を高める
✅ 仕事に役立つ情報を掲載し、実用性を持たせる
✅ 季節感を取り入れ、親しみやすい内容にする
社内報のネタ切れを防ぐ!アイデアの探し方
社内報を定期的に発行していると、「次に何を掲載すればよいのか…」とネタに困ることもあるじゃろう。
しかし、情報の収集方法や発信のコツを知っておけば、ネタ切れを防ぎ、継続的に魅力的なコンテンツを作ることができる。
効果的な情報収集と発信のコツ
1. 社内のさまざまな部署から情報を集める
✅ 他部署との連携を強化し、日々の業務や取り組みを取材する
✅ 新しいプロジェクトや成功事例を積極的にピックアップする
✅ 各部署の「今後の予定」や「改善した点」を紹介することで、全社の意識共有につなげる
例えば、
といった記事は、社員の関心を引きやすいじゃろう。
2. 社員アンケートや投票を活用する
✅ 「今、社内で気になっていること」を匿名で募集する
✅ 「○○について知りたい!」というテーマで社員投票を実施する
✅ 毎月の社内報で「読者アンケート」を行い、人気のコンテンツを把握する
例えば、
などを集計し、記事に反映すると、社員の関心が高まるのじゃ。
3. 季節や時事ネタを活用する
✅ 社内イベントや季節ごとの話題を取り入れる
✅ 業界の最新ニュースやトレンドを解説する
✅ 「○○年の振り返り」「今年の目標」といった時期ごとの特集を組む
例えば、
といった記事は、タイムリーで読まれやすいじゃろう。
4. 社内SNSや掲示板を活用する
✅ 社内SNSで社員が投稿した情報をピックアップする
✅ 掲示板で「社内報で取り上げてほしい話題」を募集する
✅ フリートーク欄を設け、社員同士が意見交換できる場を作る
例えば、
といった記事は、リアルな情報が詰まった内容になりやすい。
5. 過去の社内報を振り返り、リニューアルする
✅ 過去に人気のあった企画を再活用する
✅ 「○年前の社内報ではこんなことがあった」企画で社歴を振り返る
✅ 以前取り上げた話題をアップデートし、新しい視点で記事を作成する
例えば、
など、社内の変化を実感できるコンテンツは人気が出やすい。
ネタ切れしない社内報を作るために
✅ 他部署や社員の意見を積極的に取り入れる
✅ アンケートや投票を活用し、関心の高いテーマを探る
✅ 季節や時事ネタを活用し、タイムリーな話題を提供する
✅ 社内SNSや過去の社内報を振り返り、情報をアップデートする
社内報作成の際に活用できるツールと広報戦略
読まれる社内報を作るには、単に記事を作成するだけでなく、発信方法やデザイン、ツールの活用も重要じゃ。
特に、デジタルツールを活用することで、社内報の制作・発行が効率化され、社員の閲覧率も向上する。
Web発信やデジタルツールの活用法
1. 社内報作成に役立つツール
✅ Canva / Adobe Express(デザイン作成)
→ テンプレートを活用して、プロ品質のデザインを簡単に作成できる
✅ Googleドキュメント / Notion(記事作成・コラボレーション)
→ チームでの原稿作成や編集作業がスムーズに行える
✅ WordPress / Note / SharePoint(Web社内報)
→ 紙ではなく、Web版の社内報を発信することで、より多くの社員に読んでもらえる
✅ SurveyMonkey / Googleフォーム(アンケート収集)
→ 社員の意見やフィードバックを簡単に集められる
✅ Slack / Teams(社内コミュニケーションツール)
→ 社内報の更新を通知し、社員に素早く情報を届ける
2. Web社内報を活用するメリット
✅ スマホやPCでいつでも閲覧可能(紙の社内報と違い、手軽に読める)
✅ 検索機能を活用し、過去の記事も簡単に参照できる
✅ 動画や画像を組み込んで、視覚的にわかりやすいコンテンツを作れる
✅ アクセス解析が可能になり、どの記事がよく読まれているか把握できる
3. 社内報の発信戦略を考える
✅ 紙とデジタルの併用で、より多くの社員に届ける
✅ 定期的な更新を行い、「次も読みたい」と思わせる仕組みを作る
✅ メールや社内SNSで更新情報を通知し、読んでもらう機会を増やす
✅ 特集記事や人気企画を定期的に再掲し、新しい社員にも読んでもらう
効果的な広報戦略を立て、社内報の価値を高める
✅ デジタルツールを活用し、作成・発信の手間を削減する
✅ Web社内報を活用し、社員がどこからでもアクセスできる環境を作る
✅ 発信の仕組みを整え、社員が継続的に社内報を読む習慣をつける
まとめ:社員に読まれる社内報を作るために
社内報は、企業文化の醸成や社員間のコミュニケーションを促進する重要なツールじゃ。
しかし、読まれない社内報になってしまっては、せっかくの労力も無駄になってしまう。
そのため、社員の関心を引き、積極的に読まれる社内報を作る工夫が必要じゃ。
読まれる社内報を作るポイント
✅ 目的を明確にし、情報の方向性を定める
→ 「何を伝えたいのか?」を明確にし、社内報の目的に沿った内容を発信
✅ 社員が参加しやすい企画を増やす
→ 社員インタビューやアンケートを活用し、当事者意識を持たせる
✅ 季節や時事ネタを取り入れ、親しみやすい内容にする
→ 定番ネタに加え、最新トレンドや季節感を意識した企画を盛り込む
✅ デジタルツールを活用し、閲覧しやすい環境を作る
→ 紙の社内報に加え、Webや社内SNSを活用し、より多くの社員に情報を届ける
効果的な社内報運営のために
社内報は、単なる情報発信ツールではなく、社員のモチベーション向上や組織の活性化にもつながる。
そのため、社内の声を反映しながら、継続的に改善していくことが重要じゃ。
読者の関心を引き、より効果的な社内報を作成するために、本記事で紹介したポイントをぜひ活用されよ。
FAQs
Q1.社内報のネタが思いつかないときはどうすればいいですか?
A1:
✅ 社員アンケートを実施し、興味のあるテーマを募集する
✅ 過去の社内報を振り返り、人気のあった企画をリニューアルする
✅ 他部署との連携を強化し、新しい取り組みや成功事例を取材する
✅ 業界ニュースやトレンドを取り入れ、最新情報を発信する
Q2.紙とデジタルのどちらで社内報を作るのがよいですか?
A2:
どちらにもメリットがあるため、ハイブリッド運用が推奨される。
✅ 紙の社内報 → 手軽に読める・デスクや休憩室に置ける
✅ デジタル社内報(Web・社内SNS) → どこからでも閲覧可能・検索機能や動画活用ができる
Q3.社員が積極的に読んでくれる社内報を作るには?
A3:
✅ 社員が関わるコンテンツを増やし、当事者意識を持たせる
✅ デザインを工夫し、読みやすくする(写真やイラストを活用)
✅ アンケートやコメント機能を設け、双方向のやりとりを促す
Q4.社内報の発行頻度はどのくらいが適切ですか?
A4:
✅ 月刊(毎月発行) → 最新情報やタイムリーな話題を発信できる
✅ 隔月刊(2か月ごと) → 内容を充実させつつ、負担を軽減できる
✅ 季刊(3か月ごと) → じっくり作り込んだ特集記事を掲載しやすい
Q5.社内報の効果を測る方法はありますか?
A5:
✅ Web版の閲覧数やクリック率を分析する
✅ 社員アンケートを実施し、満足度や改善点を収集する
✅ 社内SNSの反応やコメント数をチェックする